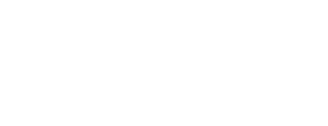食べる
ドリンク
-
食道楽のカフェ
芝生と入鹿池を眺めながらのんびりしたひとときを
場所
第四高等学校武術道場「無声堂」横(4丁目)
ジャンル
お食事処
予算
~1000円 ※クレジットカード・電子マネー・QRコード決済をご利用いただけます。
予約
予約不可
more
-
デンキブラン汐留バー
デンキブランやラフカディオ珈琲が楽しめるバー
場所
工部省品川硝子製造所1階(4丁目)
ジャンル
バー
予算
~600円 ※クレジットカード・電子マネー・QRコード決済をご利用いただけます。
more
-
京甘味処なか井茶寮
造り酒屋だった風情ある建物で楽しむ甘味処
場所
京都中井酒造内(2丁目19番地)
ジャンル
喫茶店
予算
~800円 ※クレジットカード・電子マネー・QRコード決済をご利用いただけます。
予約
予約不可
more
-
帝国ホテル喫茶室
名建築内の空間で過ごす贅沢なカフェタイム
場所
帝国ホテル中央玄関(5丁目67番地)
ジャンル
喫茶店
予算
~1200円 ※クレジットカード・電子マネー・QRコード決済をご利用いただけます。
more
-
食道楽のコロツケーの店
食べ歩きにぴったり
場所
帝国ホテル中央玄関前芝生広場(5丁目)
ジャンル
軽食・ドリンク
予算
~600円 ※クレジットカード・電子マネー・QRコード決済をご利用いただけます。
more
-
正門テラス
明治村人気の食べ歩きグルメ
場所
大井牛肉店横(1丁目)
ジャンル
軽食・ドリンク
予算
~600円 ※クレジットカード・電子マネー・QRコード決済をご利用いただけます。
予約
予約不可
more
-
食道楽のカレーぱんの店
明治時代小説「食道楽」のレシピを元に創作した「カレーぱん」が人気
場所
札幌電話交換局前広場(2丁目)
ジャンル
軽食・ドリンク
予算
~600円 ※クレジットカード・電子マネー・QRコード決済をご利用いただけます。
more
おすすめスポット
- RECOMMENDED -