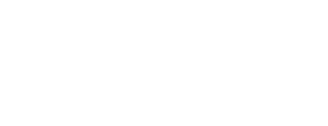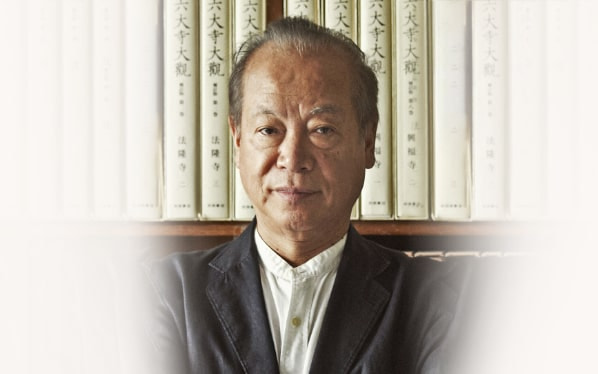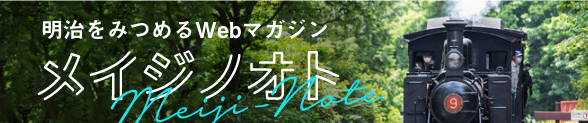明治という時代
明治ってどんな時代?
はじまりの時代
日本の「明治時代」は、私たちが暮らす「現代」の礎(いしずえ)が築かれた時代です。
例えば、日本で初めて電灯が灯ったのも、鉄道が走ったのも明治時代です。1日が24時間、1年が365日になったのも明治時代。子供達は小学校へ通うようになり、大人達が新聞を読むようになったのも明治時代。日本初の選挙も国会も、明治時代に行われました。
今の私たちにとって当たり前の「制度」や「生活」は、その多くが明治時代から始まっています。

いざ開国!
明治が始まる前、長く「鎖国」の状態にあった日本は、1853年、黒船の来航とともに世界と出会いました。欧米の強国がアジアに迫り来る中、日本は西洋の制度や文化を取り入れた「近代国家」への道を歩みます。
驚くべきは、その歩みの速さ。郵便制度の導入は明治4年、鉄道開通、小学校教育開始、富岡製糸場稼働は明治5年、自由民権運動が始まったのが明治7年です。
急激な変化の中では混乱もありましたが、西洋からの新しい価値観を柔軟に受け入れ、日本古来のものと組み合わせながら、世界に類を見ない速度で大変革を遂げたのです。そんなエネルギーに満ち溢れた日本の「青春時代」、それが明治時代です。

こんなものが
日本にできたのも明治時代
-
 鉄道
鉄道
-
 郵便局
郵便局
-
 小学校
小学校
-
 電気
電気
-
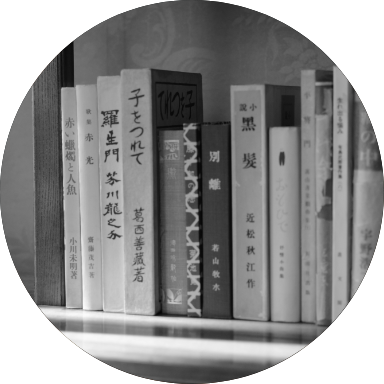 博物館
博物館
図書館 -
 銀行
銀行
-
 病院
病院
-
 ホテル
ホテル
etc…
「明治時代」と「建築」
「強=構造・素材」の変化
日本の建築は、古来より木造が主体であり、古くは中国大陸からの仏教の伝来とともに工法、構造技術を取り入れ、長い期間をかけて独自に成熟させていったものでした。
明治時代に入ると、西洋の建築技術であるトラス構造(=複数の三角形で構成され、節点がボルト等で固定された骨組構造)が屋根の骨組みに取り入れられ、長大な木材を用いずとも一室の大空間を設けることが可能になりました。
そして、新たな素材として「レンガ」「石材」が取り入れられ、木材と併用、あるいは木材にとって代わり、これら新素材ならではの「アーチ構造」を用いた新たな建造物を出現させました。
また、レンガ造や石造に対し耐震性の点で信頼が揺らぎ始めた明治時代後半には、鉄筋コンクリート造が徐々に導入されていきます。


一方、新たな素材としては、「板ガラス」の出現も大きな変化でした。これまで紙張りの障子が、ガラス嵌め込みの窓となり、新たな美意識とともに、「ステンドグラス」といった装飾も導入されました。
また、仕上げの塗装材、いわゆる「ペンキ」は、建築に新たな色彩を与え、木目塗り、マーブル塗りといった変わり塗りの技法は、新たな建築空間の創出に寄与しました。


さらに、「タイル」「テラコッタ」といった装飾用陶器の存在も忘れてはいけません。タイルは、初期は輸入に頼っており、暖炉などの限られた箇所に使われていましたが、建築構造が「レンガ造」から「鉄筋コンクリート造&タイル張り仕上げ」へと移行する時期に国産化され、建築物の外壁を覆うこととなります。テラコッタは、西洋の伝統的建築における装飾を模倣的に再現するだけでなく、幾何学的デザインが取り入れられ、後の帝国ホテル・ライト館において爛熟をみせることになります。
これらの装飾的な新素材は、建築における新たな「美=スタイル・空間」にも絶えず影響を与えてきました。
「用=用途・機能」の変化
「富国強兵」「殖産興業」といった政策の求める所による、近代的な「工場」や「兵舎」、
「鉄道駅舎」や「灯台」などの建設。
「廃藩置県」「憲法制定」といった統治制度の変更による、「官庁舎」「裁判所」「監獄」の建設。教育制度の導入により、
「学校」「博物館」「図書館」などの整備。
新たな社会的サービスとして、「郵便局舎」「電信電話交換局」「病院」「銀行」「ホテル」「劇場」などが誕生し、
禁教令の廃止による、居留地のみに限られていた「教会堂」の各地への拡散。



このようにして、それまで日本人が見たことも作ったこともない種類の建築が、明治時代に数多く出現することになりました。そこで活躍したのが、いわゆる「御雇い外国人」と呼ばれる外国人技術者たちです。
一方、人々が暮らす「住宅」における西洋化は、まずは外国人の住まいである居留地住宅として、のちに政府高官や財界人たちの迎賓館として「西洋館」が多く建てられることで発展を遂げていきました。同時に椅子式の生活スタイルも持ち込まれ、段階的に庶民の住宅にも浸透していったのです。
「美=スタイル・空間」の変化
明治時代において、建築の「美」は、常に最重要課題として認識されていました。「不平等条約の改正」という明治政府発足以来の課題を解決するには、西洋諸国に引けを取らない美しさを持つ西洋建築群を、自らの手で創出することが必須と考えられたためです。
そこで、明治10年(1877)、政府はイギリスから若き建築家ジョサイア・コンドルを招き、本格的な建築教育体制を構築。建築教育の賜物として登場した「建築家」という新たな職能の指揮のもとに、西洋風の美しい「官庁舎」や「学校」などが、次々と姿を現しました。


しかし、市中に建てられたのは、正規の建築教育を受けた「建築家」によるものだけではありません。外国人居留地を見聞きした大工棟梁たちが、独自の努力で体得した西洋風スタイルを木材や土壁など江戸期からの伝統的な素材、構造を駆使して形にしている例も数多くありました。これらは「擬洋風建築」と呼ばれ、明治初期の東京を中心とした官民施設で大きく花開きます。
明治時代も中頃を過ぎると、西洋建築スタイルのさらなる理解への欲求は、当時の西洋諸国における最新の建築スタイル潮流へもその対象を広げていきます。「アール・ヌーヴォー」「セセッション」「表現主義」といった、当時世界でも最先端の建築スタイルが、日本国内における第2世代の建築家たちによって紹介、実践されていきました。


こうしたなか、社寺、茶室、和風住宅など、明治以前からの伝統的木造工法が使用された建築にも、構造、平面計画、素材、装飾など、部分的要素に西洋的な要素が取り込まれるようになります。例えば、住宅においては、生活の場である和館と接遇空間である洋館が並列する折衷的なスタイルも浸透するようになりました。
このような急激な変化を可能としたのは、明治以前の江戸期における高度な社会システムや教育システム、大工・左官などの高度な建築技術という基盤があったからこそです。また、明治時代に生きた人々の、新奇なものを取り入れる貪欲で柔軟な姿勢も忘れてはいけません。
明治時代の建築が興味深いのは、「強」、「用」、「美」のどの切り口から切り取っても、極めて多種多彩である点にあり、それらは45年という短い期間の中で、施主や設計者の嗜好性と、社会の変化、地震や火災などの出来事とが絡み合いながら、螺旋状に展開されています。個々の建築と向き合いながらその螺旋をたどっていくと、まさに無数のストーリーを垣間見ることができるのですが、この作業は、まさに「謎解き」のようでもあり、興味がつきません。
皆さんも、博物館明治村の60を超える近代建築群に触れながら、この「謎解き」にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
時代背景と年表
政治
文化
文明
文学
| 1853年(嘉永6年) | ペリーが浦賀(神奈川県)に来航 | |
| 1854年(安政元年) | 日米和親条約を締結する | |
| 1858年(安政5年) | 日米修好通商条約を締結する | |
| 1867年(慶応3年) | 徳川慶喜が大政奉還を行う | |
| 1868年(明治元年) | 9月8日 | 「明治」と改元し一世一元の制を定める |
| 1871年(明治4年) | 廃藩置県が行われる | |
| 1873年(明治6年) | 7月28日 | 地租改正条例を布告 |
| 1874年(明治7年) | 1月15日 | 東京警視庁ができる |
| 1877年(明治10年) | 2月15日 | 一万三千の鹿児島士族、 西郷隆盛を擁して武装決起 (西南戦争勃発) |
| 1877年(明治10年) | 9月24日 | 西南戦争終幕 |
| 1878年(明治11年) | 5月14日 | 大久保利通暗殺される |
| 1879年(明治12年) | 8月31日 | 明治天皇の皇子として後の 大正天皇ご誕生 |
| 1882年(明治15年) | 4月6日 | 板垣退助 岐阜の自由懇談会で 刺される |
| 1885年(明治18年) | 12月22日 | 初代総理大臣に伊藤博文 |
| 1889年(明治22年) | 2月11日 | 大日本帝国憲法公布 |
| 1890年(明治23年) | 11月29日 | 帝国議会開設 |
| 1894年(明治27年) | 7月25日 | 日清戦争開戦 |
| 1895年(明治28年) | 4月17日 | 日清講和条約調印(下関条約) |
| 1900年(明治33年) | 5月10日 | 皇太子(後の大正天皇)ご成婚 |
| 1901年(明治34年) | 4月29日 | 大正天皇の皇子として後の昭和天皇ご誕生 |
| 1902年(明治35年) | 7月18日 | 西郷従道 没(1843~1902) |
| 1904年(明治37年) | 2月10日 | 日露戦争開戦 |
| 1905年(明治38年) | 5月27〜28日 | 日露戦争、日本海海戦 |
| 1905年(明治38年) | 9月4日 | 日露講和条約調印(ポーツマス条約) |
| 1906年(明治39年) | 1月7日 | 西園寺公望内閣成立(第一次) |
| 1906年(明治39年) | 3月31日 | 鉄道国有法が成立 |
| 1908年(明治41年) | 4月28日 | 初のブラジル移民781人が神戸港から笠戸丸で出港 |
| 1909年(明治42年) | 10月26日 | 満州のハルピン駅で伊藤博文暗殺 |
| 1912年(明治45年) (大正元年) |
7月30日 | 明治天皇崩御、「大正」と改元 |
| 1871年(明治4年) | この頃より牛鍋屋がにぎわう | |
| 1872年(明治5年) | 2月21日 | 東京日日新聞、東京最初の日刊紙として定期購読者に宅配 |
| 1872年(明治5年) | 11月9日 | 「西洋料理指南」でカレーがはじめて紹介される(出版物で初めて登場) |
| 1883年(明治16年) | 11月29日 | 鹿鳴館の開館式 |
| 1887年(明治20年) | 4月 | 鹿鳴館で首相主催の仮装舞踏会開く(欧化主義への非難高まる) |
| 1893年(明治26年) | 神谷傳兵衛が浅草「みかはや銘酒店」で日本初のカクテルを発売 | |
| 1904年(明治37年) | 12月21日 | 日本発のデパート三越呉服店開業 |
| 1904年(明治37年) | 婦人の髪型「二〇三高地」が流行 | |
| 1905年(明治38年) | 東京で日露講和反対国民大会開催(日々谷焼き討ち事件) | |
| 1906年(明治39年) | 12月15日 | 年賀郵便取扱制度創設、同日受付開始 |
| 1907年(明治40年) | 1月31日 | 乃木希典大将が学習院長に就任 |
| 1911年(明治44年) | 1月12日 | レルヒ少佐、高田でスキーを指導 |
| 1869年(明治2年) | 東京~横浜間で電信事業が開始される | |
| 1872年(明治5年) | 9月12日 | 新橋~横浜間、鉄道開業 |
| 1872年(明治5年) | 11月9日 | 太陽暦を採用(翌年から実施) |
| 1874年(明治7年) | 8月6日 | 二階建て乗合馬車運行 |
| 1882年(明治15年) | 6月25日 | 東京馬車鉄道会社開業、 新橋~日本橋間開業 |
| 1887年(明治20年) | 4月 | 大型の二輪車(自転車)が流行 |
| 1889年(明治22年) | 7月1日 | 東海道線全通(新橋~神戸)、 時刻表と賃金定まる |
| 1890年(明治23年) | 12月16日 | 東京市内と横浜市内及び両市間での電話交換業務が開始 |
| 1894年(明治27年) | 8月25日 | 北里柴三郎 ペスト菌発見 |
| 1895年(明治28年) | 2月1日 | 京都で市街電車開業 (京都~伏見間仮開業) |
| 1899年(明治32年) | 加藤サルトリ博士によりインスタントコーヒー発明 | |
| 1903年(明治36年) | 11月22日 | 京都で乗合バスが営業開始 |
| 1904年(明治37年) | 9月2日 | 戦勝祝賀、イルミネーション電車運転 |
| 1904年(明治37年) | 9月26日 | 日本に帰化した小泉八雲 (ラフカディオ・ハーン)没 (1850~1904) |
| 1908年(明治41年) | 4月8日 | 日本式気球を完成、 仏・独製に勝る |
| 1910年(明治43年) | 5月19日 | ハレー彗星が地球に最接近 |
| 1912年(明治45年) | 4月15日 | 豪華客船タイタニック号 沈没 |
| 1890年(明治23年) | 1月 | 森鴎外「舞姫」を雑誌「国民の友」に発表 |
| 1891年(明治24年) | 11月7日 | 幸田露伴「五重塔」連載開始 |
| 1901年(明治34年) | 8月 | 与謝野晶子「みだれ髪」刊行 |
| 1903年(明治36年) | 11月22日 | 報知新聞で日本初のグルメ小説「食道楽(村井弦斎著)」が連載される |
| 1905年(明治38年) | 1月 | 夏目漱石「吾輩は猫である」連載開始 |
| 1909年(明治42年) | 12月15日 | 竹久夢二「夢二画集」出版 |
| 1910年(明治43年) | 12月1日 | 石川啄木「一握の砂」が刊行 |
| 1912年(明治45年) | 4月13日 | 石川啄木 没(1886~1912) |