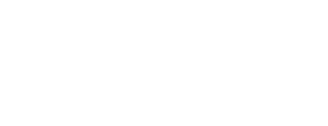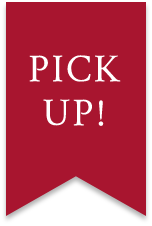体験する
4丁目
-
スリル満点!暗闇迷路
暗夜回廊
スリル満点!暗闇迷路
場所
歩兵第六聯隊兵舎2階|4丁目36番地
開催日
土日祝のみ営業 ♦営業時間13:00~15:00
予約
予約不要(現地でご案内)
所要時間
制限時間:4分
more
-
建物スタンプを集めながら楽しく村内めぐり
明治村スタンプラリー
建物スタンプを集めながら楽しく村内めぐり
場所
村内各所
開催日
明治村営業日に準ずる
予約
予約不要
more
-
乗車体験ができる国内最古の路面電車
京都市電 乗車体験
乗車体験ができる国内最古の路面電車
場所
市電名古屋駅・京都七条駅・品川燈台駅(それぞれ4・2・3丁目)
予約
予約不要(現地にてご案内)
所要時間
1区間につき約3分
more
-
音声ガイダンスとともにゆっくり走るレトロなバス
村営バス
音声ガイダンスとともにゆっくり走るレトロなバス
場所
村内9つの停留所(村内地図をご参照ください)
予約
予約不要(現地でご案内)
所要時間
正門⇔帝国ホテル間約20分
more
-
10年後の"自分"や"大切な人"へメッセージ
はあとふるレター
10年後の"自分"や"大切な人"へメッセージ
場所
宇治山田郵便局舎 簡易郵便局(4丁目46番地)
more
-
古き良き遊びを体験!
射的
古き良き遊びを体験!
場所
歩兵第六聯隊兵舎2階|4丁目36番地
開催日
毎日営業!◆営業時間 10:00~17:00
予約
予約不要(現地でご案内)
more
-
古き良き遊びを体験!
矢場
古き良き遊びを体験!
場所
歩兵第六聯隊兵舎2階|4丁目36番地
開催日
土日祝のみの営業となります。◆営業時間 10:00~17:00
予約
予約不要(現地でご案内)
more
-
学芸スタッフによる案内付きで巡るガイドツアー
プレミアムガイド(事前予約制)
学芸スタッフによる案内付きで巡るガイドツアー
場所
村内各所
開催日
GWおよびお盆期間等の多客時、3が日を除く
予約
事前予約制|ご利用予定日の1か月前から7営業日前まで
所要時間
90分間(移動時間含む)
more
おすすめスポット
- RECOMMENDED -