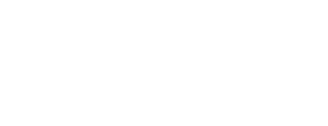見る・知る
名鉄電車の発展により誕生した変電所
名鉄岩倉変電所
名古屋市内では京都市電に遅れること3年、明治31年(1898)に開通した名古屋電気鉄道により、市内電車が走り始めました。同社はその後も尾張地区に路線を伸ばし、大正元年(1912)には犬山線を開通。その時に建てられたのが、この「岩倉変電所」です。
建物は、内部に大きな変電用機械が入れられるように、背の高いレンガ造りに。出入り口や縦長の大きな窓は、半円のアーチ型。褐色の塩釉系のレンガを、上下4段の帯に入れています。建物四隅にはバットレス(控壁)が取り付きます。
| 建設年 | 明治45年(1912) |
| 村内所在地 | 5丁目66番地 |
| 旧所在地 | 愛知県岩倉市下本町 |
| 文化財種別 | 登録有形文化財 |
| 登録年 | 平成16年(2004) |
| 解体年 | 昭和49年(1974) |
| 移築年 | 昭和50年(1975) |

目次 - Index -

鑑賞ポイント
ポイント01|木造クイーンポストトラスの小屋組

小屋裏を露出させた小屋裏あらわしになっています。
ポイント02|設計者の遊び心があふれる、レンガ積みの装飾

変電所の背面は、他の3面と趣が異なり、様々なレンガ積みの手法を用いた装飾が施されています。半円アーチ、円弧アーチ、柱型、凹みなど、設計者の楽しみの跡がうかがわれるようです。この面に碍子(がいし)が付き、架線に電気が送られていました。


縦長の窓には上げ下げの建具が建て込まれ、上部に半円形の欄間がつけられています。窓によって切り取られた村内5丁目の風景もぜひお楽しみください。
紹介動画
村内 Googleマップ
村内の場所
ストリートビューで見学
近くのグルメ・ショップ
- GOURMET & SHOPS -