見る・知る
和洋意匠を巧みに折衷した、商人一家の別荘
芝川又右衛門邸
現在の兵庫県西宮市甲東園に建てられた、大阪の商人であった芝川又右衛門の別荘。設計者は当時の京都工等工芸学校の図案科で主任を務め、のちに京都帝国大学建築学科の創設者となる武田五一でした。
建物は木造2階建てのスペイン瓦葺き。1階は開放的なベランダに、外へ張り出したボウウィンドウを設けるなど洋風の造りになっています。それとは対照的に2階は和風としつつも、 1、2階に一体感をもたせてまとめています。武田五一の設計による、和洋意匠を折衷した住宅の好例といえるでしょう。
| 建設年 | 明治44年(1911) |
| 村内所在地 | 3丁目68番地 |
| 旧所在地 | 兵庫県西宮市上甲東園 |
| 文化財種別 | 登録有形文化財 |
| 登録年 | 平成20年(2008) |
| 解体年 | 平成7年(1995) |
| 移築年 | 平成19年(2007) |

目次 - Index -

鑑賞ポイント
ポイント01|ヨーロッパで流行した新時代の様式


建物全体のプロポーションはもちろん、2階和室の出窓に配された柱間装置、上げ下げ窓、建物正面と背面についた煙突、また照明器具などのデザインからは、武田五一がヨーロッパで影響を受けたセセッション式の印象が見られます。
武田五一は明治34年(1901)から約2年半、ヨーロッパへ留学。帰国直後、貿易商であった福島行信の依頼を受け、当時欧米で流行していたアール・ヌーボー様式を日本で初めて取り入れた住宅を設計しました。
その後、議院建築視察のため再度欧米を訪問。帰国後、芝川又右衛門より「洋館」の設計依頼を受けて、ヨーロッパのグラスゴー派やウィーンのセセッション式に、数寄屋など日本建築の伝統を融合したこの洋館を建てたと言われています。
ポイント02|洋の中に見る和、和の中に見る洋


1階ホールは洋風の漆喰壁に網代(あじろ)と葦簾(よしず)を市松状に用いた天井が配され、数寄屋建築における伝統技法が駆使されています。一方、2階の座敷には襖戸の奥に暖炉が設けられています。

移築秘話
阪神淡路大震災をきっかけに、明治村へ寄贈

平成7年(1995)の阪神淡路大震災で被災し解体を余儀なくされ、同年に明治村に寄贈されました。
平成17年(2005)に博物館明治村の開村40周年記念として復原事業を起こし、平成19年(2007)に竣工、同年9月より展示公開がはじまりました。

外観の古写真から、この建物は創建当初、外壁が杉皮張りで仕上げられていたことが判明しています。一方で昭和8年(1933)発行の「武田博士作品集」に掲載されている写真を見る限り、外観はスパニッシュ風の仕上げになっています。昭和2年(1927)の和館の増築にともない、洋館の外装などが現在のような姿に大きく変更されたようです。
移築にあたっては、「作品集」に掲載されている姿に復原することが目指されました。
More Detail
さらに詳しく知る
「博物館 明治村」に潜む、 隠れハートマークを探しに行こう!
「博物館 明治村」に潜む、 隠れハートマークを探しに行こう!
愛らしく、馴染みのある「ハートマーク」。
みなさんは、ハートマークにどのようなイメージをお持ちでしょうか。「心臓」のほかに「愛情」や「恋愛」といった「愛」を連想するイメージが強いのでは?そんなハートマークが「愛」を表現するモチーフとして日本にもたらされたのは、明治時代であったといわれています。
レトロでモダン! 明治時代を照らす明かり
レトロでモダン! 明治時代を照らす明かり
普段、何気なく使っている照明。スイッチひとつでパッと明るくその場に光を差し込み、私たちの暮らしを照らしてくれます。街を歩けばいたるところにライトや街灯があって、真っ暗な夜でも手ぶらで歩くことができます。私たちの身の回りには、暮らしをより豊かにしてくれる、そんな明かりたちが当たり前のように存在します。では、電気やガスのなかった時代を生きた人たちが、どのようにして暗闇に明かりを灯していたのでしょうか。
村内 Googleマップ
村内の場所
ストリートビューで見学
近くのグルメ・ショップ
- GOURMET & SHOPS -


























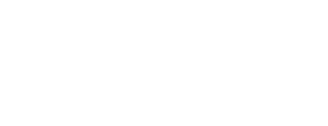
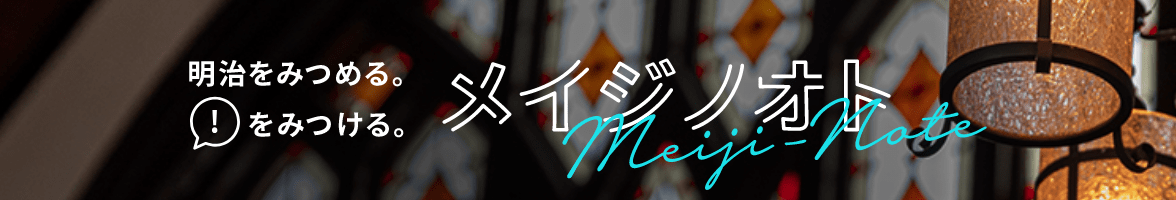
 予約不要(現地でご案内) 建物保護のため人数を制限する場合があります。
予約不要(現地でご案内) 建物保護のため人数を制限する場合があります。 

