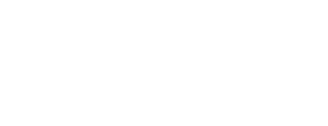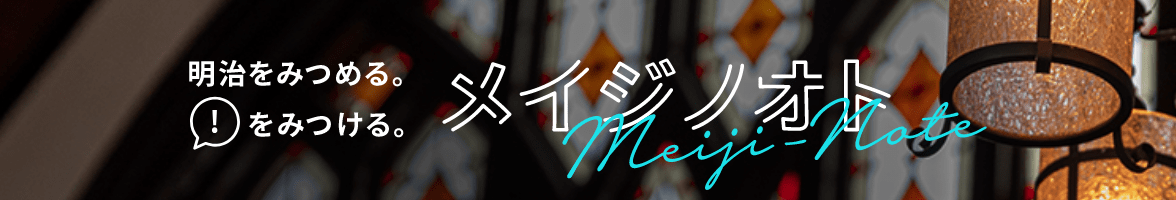見る・知る
八角形の看守所と監房
金沢監獄中央看守所・監房
金沢監獄は明治5年(1872)制定の「監獄則並図式」に沿って造られた監獄。八角形の看守所を中心に5つの監房棟が放射状に並ぶ洋式の配置でした。そのうち中央看守所と独居房として使用された監房の一部分が移築されました。なお中央に置かれている監視室は網走監獄で使用されたものです。
監視室からは各監房棟の中廊下が一望に見渡せ、外部については看守所上部の見張り櫓から監獄全域の状況を把握できるため、管理上非常に効果的でした。
| 建設年 | 明治40年(1907) |
| 村内所在地 | 5丁目62番地 |
| 旧所在地 | 石川県金沢市小立野 |
| 文化財種別 | 登録有形文化財 |
| 登録年 | 平成16年(2004) |
| 解体年 | 昭和46年(1971) |
| 移築年 | 昭和47年(1972) |

目次 - Index -

鑑賞ポイント
ポイント01|中央から舎房を見渡す見張所

中央看守所の中央には、直径3.3mの監視室が置かれ、ここから各舎房の廊下がひと目で見渡せるようになっていました。現在、明治村に置かれている監視室は金沢監獄のものではなく、網走監獄で使われていたものです。
中央看守所は柱のない八角形の造りで、直径14mの大広間。大広間の天井は、建物の八角形状に沿って天井板が張られています。中央を折り上げ、段差を利用した換気口が設けられています。
ポイント02|中央看守所の屋根には見張塔が

四角形の見張り櫓は、四方にガラスの建具をはめ、屋根は宝形で四辺の軒の中央を折り上げたもの。頂部の棟飾や腰壁のデザインなどに、工夫の跡が見られます。
ポイント03|廊下の左右に、監房の重厚な扉が並ぶ


広い中廊下の左右には、独居監房の重い扉が整然と並びます。扉の上にある換気用の高窓から、独房内の衛生面への配慮がうかがえます。
ここで一緒に見られるもの
村内 Googleマップ
村内の場所
ストリートビューで見学
近くのグルメ・ショップ
- GOURMET & SHOPS -