記者
ライター安田淳
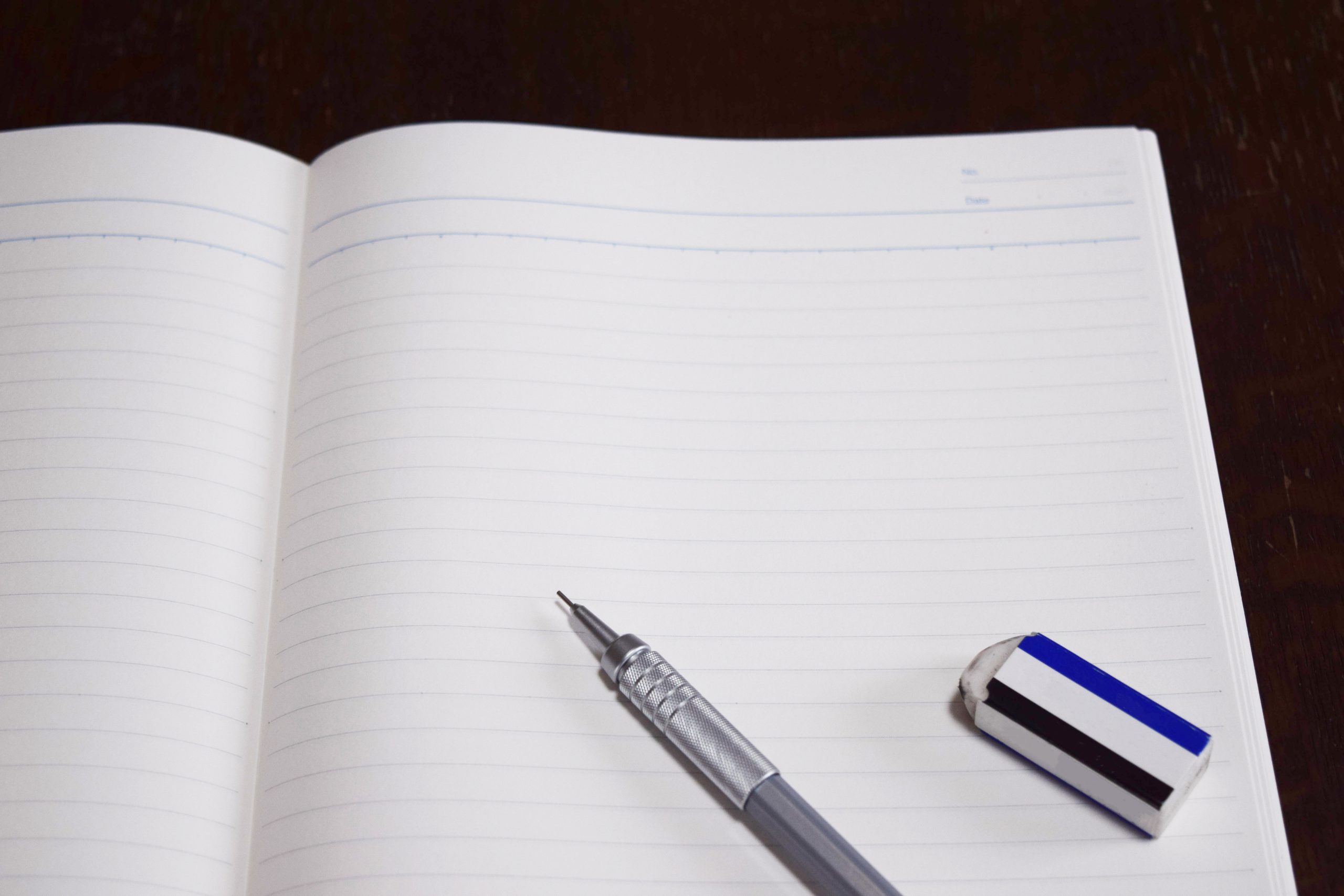
2022/01/31
「現在では当たり前のように存在するけれど、一般的になったのは明治以降」なんていう物事が、私たちの身の回りには意外に多くあります。「〇〇のルーツは明治時代から」シリーズでは、明治時代の日本に浸透し現代社会にも根付いているさまざまな物事を、ジャンルを超えて紹介していきます。今回は「ノートの歴史」についてのお話。
横罫線が入ったシンプルなノートのことを、一般的に「大学ノート」なんて呼んだりします。私も職業柄、大学ノートは必須アイテムです(超走り書きなので罫線がほとんど意味を成していませんが)。
小学校低学年のときは、昆虫や植物が表紙に描かれた某学習帳を使っていた記憶がありますが、いつしか「大学ノート」を使うように。飾り気のない洗練されたデザインの大学ノートを使うことは、大人の階段を登る第一歩だったようにも思います。
ところで、小学生も中学生も高校生も、大学生だったころを遠い昔に感じている私のようなおじさんも愛用しているノートを、なぜ「大学ノート」と呼ぶのでしょう?

Bunkyo, Tokyo, Japan – March 11, 2017: Yasuda Auditorium: Yasuda Auditorium of University of Tokyo. The University of Tokyo is the best research university in Japan.
まず、「大学ノート」を最初に世に広めたのは、東京帝国大学(現・東京大学)の赤門前にかつて存在した文具・洋書店の「松屋」だったと伝えられています。
明治17(1884)年に留学帰りの東京大学の教授からの勧めで、当時としては珍しい洋紙を英国から輸入し、手造りで綴じ合わせたのがはじまりなのだとか。異国からさまざまなモノや文化が日本に流入した明治時代。「ノート」もその例外ではなかったのですね。
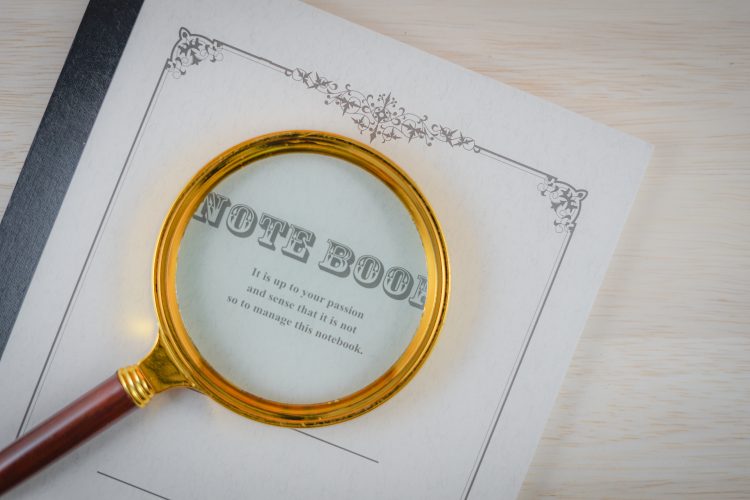
実は「大学ノート」の語源について、明確なことはわかっていないよう。いくつか説はあり、
これはきっと間違いではないはず!「大学ノート」というネーミングが学生の間でおしゃれなものとして流行ったことも、なんだか容易に想像できます。
現在でこそどこでも安価で手に入るものですが、当時貴重だった洋紙が複数枚綴じられた大学ノートが高価だったことは想像に難くありません。ある種の憧れやステータスだったのでしょう。明治17(1884)年にノートが売り出された時に、一冊の値段は7〜8銭ほどだったと言うので、現代で言うと1,400円~1,600円くらいでしょうか。なかなか高価で、無駄には使えませんね。

昨今ではより文字を整えやすいよう方眼罫のものが主流になっていたり、スマホと連携したノートが売られていたり、文具売場を訪れるたびに楽しい発見があります。
ペーパーレス化が叫ばれる今日この頃、パソコンの画面に直接文字を書き入れたりする機会も増えてきました。しかしながら、ノートを完全に手放せる未来は現在のところとても想像できず……。これからもきっとお世話になります。

記者
ライター安田淳
PICK UP