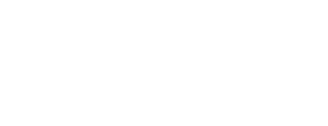見る・知る
八雲が夏に過ごした海辺の町家
小泉八雲避暑の家
小泉八雲(1850-1904)はもとの名をラフカディオ・ハーンと言い、アイルランド人の父とギリシャ人の母の間に生まれた。アイルランドで教育を受けた後、アメリカで新聞記者などを経て、明治23年(1890)に来日し、英語教師として松江中学を始め各地へ赴任しました。明治29年(1896)に日本に帰化し、同年東京帝国大学に招かれ教鞭をとるようになると、毎年夏を焼津で過ごすようになりました。この家は魚屋の山口乙吉の家で、1階に通り土間を備えた典型的な町家です。
| 建設年 | 明治初年(1868)頃 |
| 村内所在地 | 4丁目48番地 |
| 旧所在地 | 静岡県焼津市城之腰 |
| 文化財種別 | 登録有形文化財 |
| 登録年 | 平成16年(2004) |
| 解体年 | 昭和43年(1968) |
| 移築年 | 昭和46年(1971) |

目次 - Index -

偉人ストーリー
小泉八雲『乙吉の達磨』より
「(略)私の庭の雪達磨は、何年か前に、私が東海岸の或漁村で楽しい一夏を送った時に発見した甚だ妙な達磨の事を私に想ひ出させる。そこには宿屋がなかった、しかし、或魚屋の主人の乙吉と云ふ男が、私に二階を貸して、不思議な程色々に料理した魚の御馳走をしてくれた。
(略)
それから私は店へ帰って、うろうろしながら色々の物を眺めた。一方には棚が何段もあって、干物の箱、食用の海藻の包み、草鞋草履の束、酒徳利、ラムネの壜などのせてある。その反対の側のずっと上に、神棚があった。その神棚の下に、達磨の赤い像のある少し小さい棚のある事に気がついた。たしかにその像はおもちゃではなかった、その前に供物もあった。私は達磨が家の神となっているのを見ても驚かなかった。(略)」
田部隆次訳
村内 Googleマップ
村内の場所
ストリートビューで見学
近くのグルメ・ショップ
- GOURMET & SHOPS -