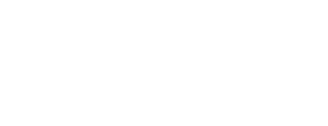見る・知る
長崎の小島で、信仰を支えた教会堂
大明寺聖パウロ教会堂
長崎湾の入口に位置する伊王島に建設されたカトリック教会堂の一つ。フランス人宣教師ブレル神父の指導のもと、大浦天主堂建設に携わった地元大工の大渡伊勢吉によって建設されました。正面の鐘楼と入口土間は、昭和20年代に信者の浄財を元に増築されたものです。
木造平屋建ての入母屋造り、桟瓦葺きでありながら、内部は後期ゴシック様式で、身廊と側廊をもつ三廊式(バシリカ式)。身廊の天井は後期ゴシックの教会堂の交差リブボールト天井を模して漆喰塗で作られています。
| 建設年 | 明治12年(1879) |
| 村内所在地 | 5丁目56番地 |
| 旧所在地 | 長崎県長崎市伊王島 |
| 文化財種別 | 登録有形文化財 |
| 登録年 | 平成16年(2004) |
| 解体年 | 昭和50年(1975) |
| 移築年 | 平成6年(1994) |

目次 - Index -

鑑賞ポイント
ポイント01|キリスト教禁制の影響を感じさせる和風の外観

明治6年(1873)、キリスト教の禁教令が解かれたことから、数年後には長崎各地や各島々に木造の小さな教会堂が建てられるようになりました。その中でも、早い例として知られるのがこの教会堂。
農家のような質素な外観ながら、内部は三廊式のゴシック様式の教会。和風の外観からは、キリスト教禁制の影響を色濃く残した時代背景を感じさせます。
本屋根より一段下がった玄関部分は、階下に入り口の土間、階上に聖歌隊席を設けました。棟上には鐘楼がのります。
ポイント02|西洋ゴシック様式の空間を木造で再現

内部には、身廊の正面に祭壇、右側廊の正面にルルドの洞窟、左側廊の突きあたりに聖具室を設置。


コロネード(列柱)は、太い円柱の周りに細い柱を束ねた「束ね柱」になっており、ブドウを彫刻した飾りが施されています。
身廊の天井は、漆喰塗りのリブヴォールト天井。側廊の天井は竿縁天井ですが、板を湾曲させて、四半円のヴォールト天井になぞらえています。身廊も側廊も一つの両流れ屋根で覆われた造り。西洋のゴシック様式建築の教会で多く見られる、トリフォリウムやクリアストーリーはありません。
ポイント03|洞窟内で浮かび上がる聖母マリアの像

ルルドの洞窟にあるマリア像の周りには、光の演出が施されています。天窓から光が落ち、像の後ろからも光が漏れる造りです。
通常は屋外に設けられることの多いルルドの洞窟が、ここでは内部にあるという珍しい例です。押入れのような凹みに小さな鳥籠状の竹小舞を編み上げ、岩のように泥を塗りつけて仕上げています。
村内 Googleマップ
村内の場所
ストリートビューで見学
近くのグルメ・ショップ
- GOURMET & SHOPS -