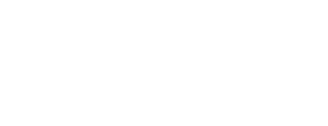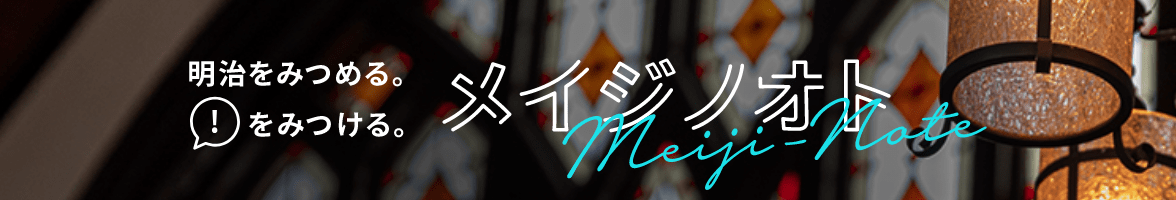見る・知る
近代古都で布教の拠点となった白亜の教会
聖ザビエル天主堂
16世紀に来日したフランシスコ・ザビエルを記念し、京都・河原町三条に建てられたカトリック教会堂。近代の京都でのカトリック布教は、明治12年(1879)、パリ外国宣教会のヴィリオン神父が入洛したことが始まりとされています。フランスの篤志家から寄付を募って資金を集め、河原町三条にあった旧大名の蔵屋敷を購入してこの教会堂が建てられました。
建設にあたり、図面はフランスから取り寄せたとも。設計は東京で在日宣教師の一人であったパピノ神父が担いました。信者であり、大阪で大工の棟梁をしていた横田彦左衛門が施工したと伝えられています。
| 建設年 | 明治23年(1890) |
| 村内所在地 | 5丁目51番地 |
| 旧所在地 | 京都市中京区河原町三条 |
| 文化財種別 | 登録有形文化財 |
| 登録年 | 平成16年(2004) |
| 解体年 | 昭和42年(1967) |
| 移築年 | 昭和48年(1973) |

目次 - Index -

鑑賞ポイント
ポイント01|美しい薔薇窓とステンドグラス

正面の薔薇窓や内陣・側廊のステンドグラスは、色ガラスに白ペンキで草花模様を描いているのが特徴。外側に透明ガラスをはめ、二重になっています。
ポイント02|ケヤキでゴシック様式の空間を再現


室内は身廊と側廊からなる三廊式で、大アーケード、トリフォリウム、クリアストーリーの3層による典型的なゴシック様式。天井は交差リブ・ヴォールト天井で、4本の柱で囲われた1つの区画の天井を、リブで四分割する四分ヴォールトとしています。柱やリブにはケヤキ材が用いられています。
小屋組および身廊の側壁は木造ですが、そのほかの壁はもともとレンガ造でした。外壁には白漆喰塗りの目地が刻まれています。
ポイント03|内陣には7体の聖像が鎮座

右から、聖ステファノ(最初の殉職者)、聖ペテロ(十二使徒の第一使徒)、聖ヨセフ(聖母マリアの配偶者)、聖フランシスコ・ザビエル、大天使ミカエル、洗礼者聖ヨハネ(キリストに洗礼を施した人)、アッシジの聖フランチェスコ(フランシスコ会創設者)が配置されています。